基礎知識
本題の見直された建築確認等に入る前に、基礎知識として、「建築物」、「建築等」及び「建築確認」について説明しておく。
建築物
建築基準法の建築物とは次のとおりである[法2条1項]。
-
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
-
 に附属する門や塀
に附属する門や塀
-
観覧のための工作物
-
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
-
 ~
~
 に設ける建築設備
に設ける建築設備
上記水色ライン箇所について、以下に補足説明をする。
-
 について
について
-
- 土地に定着
-
- ここで言う「土地」とは、地面だけでなく、建物の屋上等も含む。
-
土地に置いただけのコンテナやユニットハウス等は基礎がないので、見方によっては「土地に定着している」と言えないことから、建築物に該当しないと考える方もいる。しかし、建築基準法で言う「土地の定着」とは基礎の有無は関係なく、随時かつ任意に移動できない状態を指す。
従って、置いただけのコンテナ等は、基礎が無くても容易に移動できないことから建築物に該当する。
-
トレーラーハウスは基本的に移動可能であり、つまり土地に定着していないことから建築物に該当しないようにも思える。しかし、タイヤが付いているからと言って、随時かつ任意に移動できる状態になっていなければ、建築物に該当する。
要するに、すぐに移動可能な状態になっている必要があり、そうでない具体的な状態は次のとおり。
- タイヤがパンクしている。
- 移動に支障をきたす階段やベランダ等がある。
- 給排水等の設備の配管などが、工具なしで外すことができない。
- 適法に公道を移動できない(車検を取得していない)。
- 屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 「屋根+柱」or「屋根+壁」を有するもののことである。従って、例えばカーポートは、壁を有しないが屋根と柱を有するので建築物に該当する。
-
 について
について
-
- 附属する門や塀
- 建築物と同一敷地内にある門や塀を指す。従って、建築物がない更地に設置した塀等であれば対象外である。
-
 について
について
-
- 観覧のための工作物
- 例として野球場などが挙げられるが、例外的に屋根等がなくても建築物に該当する。
-
 について
について
-
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、・・・
- 地下街やガード下等に設けた事務所、店舗、・・・のこと。
- 括弧内の除かれる施設
-
- 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
- 鉄道関連施設は除かれる。その理由は鉄道等の関係法で安全性が担保されるからで、よって建築基準法の建築物から除かれている。
- 貯蔵槽その他これらに類する施設
-
貯蔵槽に類する施設も除かれるが、一般人に取っては、上記の鉄道関連施設より、こちらの方が遥かに重要である。
と言うのも、小規模な倉庫(物置を含む)で、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ内部に人が立ち入らないもの(奥行き1m以内又は高さが1.4m以下)については、貯蔵槽に類する施設に該当することが示されているからである[「国住指第4544号(平成27年2月27日)」及び「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(2017年度版)」より]。従って、この小規模な倉庫は建築基準法の建築物でないので、建築基準法の規制を一切受けない。
なお、この小規模な倉庫の規定は既存建築物がない更地に建築する場合でも適用されるが、同一敷地内に既存建築物がある場合であれば、床面積等の要件が付くものの内部に人が入る建築物の建築が建築確認無しに可能となる(詳細は、「※2」を参照)。
-
 について
について
-
- 建築設備
- 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針を言う[法2条1項3号]。
建築等
建築確認が必要となりうる建築物の工事※1には、建築(新築、増築、改築又は移転のこと[法2条1項13号])、大規模修繕、及び大規模模様替えがある。本解説では、これら全ての工事の総称として「建築等」と表現することにする。
各用語の意味は次のとおりである。
- 新築
- 更地(建築物のない土地)に、新たな建築物を建築すること。
- 増築
- 同一敷地内で建築物の床面積が増加すること ※2。
- 改築
- 建築物の全部又は一部を取り壊した後、従前の建築物の用途、構造及び規模と著しく異なることなく建て替えること。なお、従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。
- 移転
- 解体せずに同一敷地内で建築物を移動すること。なお、別敷地へ移動する場合は、移動先の敷地に対して新築又は増築となる。
- 大規模修繕
-
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を言う[法2条1項14号]。
なお、修繕とは、性能や品質が劣化した部分を、既存のものと概ね同じ位置 ・ 形状 ・ 寸法 ・材料を用いて造り替え、性能や品質を回復することを言う。
- 大規模様替え
-
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えを言う[法2条1項15号]。
なお、模様替えとは、同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて造り替え、性能や品質を回復することを言う。
参考までに、次の工事は大規模修繕・大規模模様替えに該当しないので、建築確認が不要である。
- 屋根葺材(瓦、スレート、金属等)のみの改修、又は既存屋根の上に新しいい屋根をかぶせる改修
- 外装材(窯業系サイディング、金属系サイディング、モルタル等)のみの改修、又は既存外壁の上に新しい外壁をかぶせる改修
- 床の仕上げ材(直接目に触れる部分の表面材料)のみの改修、又は既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる工法による改修
- 過半に至らない階段の改修、又は既存階段の上に新しいし仕上げ材をかぶせる改修
- 水回り(キッチン、トイレ、浴室等)のリフォーム
- バリアフリー化のための手すりやスロープの設置
建築確認
建築確認とは、建築物の建築等を行う際に、建築基準法及び関係法令に適合しているかを確認するための制度である。以下に、手続きの流れ及び建築確認が不要な建築物について説明する。
建築確認・検査の流れ
建築物の建築等を行う際は、確認から検査までの手続きが次の流れで進む。
- 工事着手前[法6条1項]
-
建築確認申請
 確認済証の交付
確認済証の交付

- 工事中(一部の建築物のみ)[法7条の3]
-
特定工程終了
 中間検査の申請
中間検査の申請
 中間検査合格証の交付
中間検査合格証の交付

- 工事完了(竣工)[法7条]
-
完了検査の申請
 検査済証の交付
検査済証の交付
建築確認が不要な建築物[建築基準法全般]
建築基準法の建築物に該当しないものに対し建築等を行う際は、勿論、建築確認・検査は不要となるが、建築物の建築等であっても次のものは建築確認・検査が不要となる。
- 防火地域・準防火地域以外に於ける床面積10㎡以下の増築※2・改築・移転[法6条2項]
- 文化財保護法に指定されている建築物[法3条]
- 非常災害時の応急仮設建築物[法85条]
-
建築確認が必要な建築物[法6条1項]に当てはまらない建築物
 詳細は「建築確認が不要な建築物[法6条1項関連]」を参照されたし。
詳細は「建築確認が不要な建築物[法6条1項関連]」を参照されたし。
改正による見直し
建築物の規模等により、建築確認が不要であったり、建築確認の審査の一部を省略できる特例があったりするが、建築基準法の改正により、これらの対象範囲等の見直しが行われ、2025年4月1日から施行されている。
以下に、建築確認が必要な建築物について説明し、それを踏まえた上で、見直された内容とそれに伴う影響について解説する。
建築確認が必要な建築物[法6条1項]
建築基準法6条1項に於いて、建築確認が必要な建築物の規模等が規定されていて、建築物の規模によっては地域が限定されている規定もある。従って、逆に地域が限定されている建築物を限定地域以外で建築等を行えば建築確認が不要となる。また、地域が限定されている建築物をその地域内で建築等を行えば、当然建築確認が必要になるものの、一部の審査を省略できるなどの特例がある。
今回の改正で、地域が限定されている建築物の規模が縮小された。これにより、改正前までは建築確認が不要だった(あるいは、特例を受けれた)建築物に於いて、改正後からは建築確認が必要になる(あるいは、特例を受けられなくなる)建築物が発生することになった。このことは、不動産取引きを行う上でトラブルを誘発し易くなる重要な点と考えていることから(詳細は「改正による影響」を参照)、まずは建築基準法6条1項で規定している、建築確認が必要な建築物について、改正前後に分けて下表に示す。
| 号 | 種類 | 規模 | 地域 | 工事別※1建築確認の必要・不要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 増改築 or移転 |
大規模な 修繕or 模様替 |
||||
| 1号 |
別表第1(い)欄 用途の特殊建築物 |
用途床面積200㎡超 | 全地域 |
必
|
必(10㎡)
|
必
|
| 2号 | 木造 |
高さ13m超 or 軒高9m超 |
全地域 |
必
|
必(10㎡)
|
必
|
| 3号 | 非木造 |
|
全地域 |
必
|
必(10㎡)
|
必
|
| 4号 | (規定なし) | 1~3号以外 | 都市計画区域等 |
必
|
必(10㎡)
|
不
|
| 号 | 種類 | 規模 | 地域 | 工事別※1建築確認の必要・不要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 増改築 or移転 |
大規模な 修繕or 模様替 |
||||
| 1号 |
別表第1(い)欄 用途の特殊建築物 |
用途床面積200㎡超 | 全地域 |
必
|
必(10㎡)
|
必
|
| 2号 | (規定なし) |
延面積200㎡超 |
全地域 |
必
|
必(10㎡)
|
必
|
| 3号 | (規定なし) | 1と2号以外 | 都市計画区域等 |
必
|
必(10㎡)
|
不
|
 法6条1項の条文(改正前後)
法6条1項の条文(改正前後)
以下に、法6条1項の条文を改正前後に分けて掲載するが、黄色ラインは改正前後で変更になった箇所である。
第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
第六条
建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
ちなみに、改正前の法律では、4号規模(木造の場合は2階以下かつ延面積500㎡以下、非木造の場合は平屋かつ延面積200㎡以下)の建築物のことを、建築する地域に関係なく「4号建築物」と言い、また4号建築物が建築確認で受ける特例を「4号特例」と言っていた。一方改正後の法律では、旧4号の規模の建築物が新2号と新3号に分かれ、旧4号特例は規模が縮小されたものの新3号が引き継いだ。これにより、木造・非木造に関係なく、3号規模(平屋かつ延面積200㎡以下)の建築物のことを「3号建築物」と言い、また3号建築物が建築確認で受ける特例を「3号特例」と言う。
見直された内容
改正により見直された項目として、建築確認が不要な建築物の規模、審査省略制度対象の規模、省エネ基準適合対象範囲、及び構造関係等が挙げられる。以下に、各々の見直しについて解説する。
建築確認が不要な建築物[6条1項関連]
前述で示した建築基準法6条1項の規定にあてはまらない建築物の建築等が建築確認が不要となる。
整理すると、建築確認が不要な建築物とは、都市計画区域等の区域外に於ける新3号建築物(改正前であれば旧4号建築物)である。
今回の改正により、この区域外に於ける建築確認不要な建築物の規模が、次のように縮小統一された。
- 改正前
-
-
非木造
 平屋かつ延面積200㎡以下(旧4号建築物の非木造規模)
平屋かつ延面積200㎡以下(旧4号建築物の非木造規模)
-
木造
 2階以下かつ延面積500㎡以下(旧4号建築物の木造規模)
2階以下かつ延面積500㎡以下(旧4号建築物の木造規模)
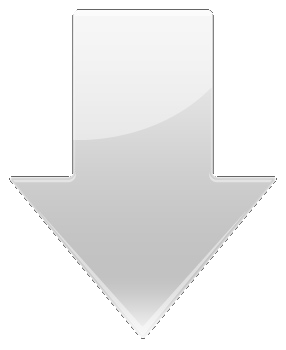
-
非木造
- 改正後
-
平屋かつ延面積200㎡以下(木造・非木造に関係なく、新3号建築物の規模として統一)
以上から、改正前までは建築確認が不要であったが改正により建築確認が必要に変わった建築物は、木造2階建て以下かつ延面積500㎡以下であり、但し平屋かつ延面積200㎡以下を除いたものである(都市計画区域等の区域外)。
なお、大規模修繕や大規模模様替えに於いて、建築確認が必要な建築物は、新1号・2号建築物(改正前であれば旧1号~3号建築物)であり、新3号建築物(改正前であれば旧4号建築物)は対象外である。従って、新3号建築物(改正前であれば旧4号建築物)に対して、大規模修繕や大規模模様替えを行う場合は、都市計画区域等の区域内であっても建築確認が不要である。
![]() 建築確認が不要な建築物の規模見直し(都市計画区域等の区域外)
建築確認が不要な建築物の規模見直し(都市計画区域等の区域外)
![]()
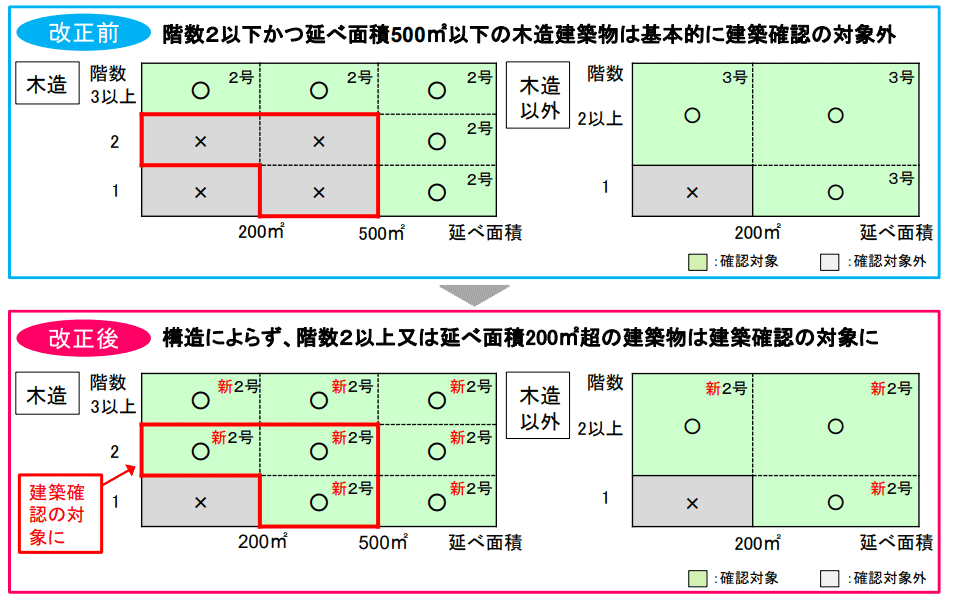
審査省略制度
審査省略制度とは、建築確認の審査に於いて、構造関係規定等の一部の審査が省略される制度である。
前述の「建築確認が不要な建築物」から分かるように、新3号建築物(改正前であれば旧4号建築物)であっても、都市計画区域等の区域内であれば、建築確認・検査が必要となる。この区域内で新3号建築物の建築等を行う場合、建築士が設計・工事監査を行えば、審査省略制度の対象となる。
つまり改正により、「建築確認が不要な建築物」と同様で、規模が次のように縮小統一された。
- 改正前
-
-
非木造
 平屋かつ延面積200㎡以下(旧4号建築物の非木造規模)
平屋かつ延面積200㎡以下(旧4号建築物の非木造規模)
-
木造
 2階以下かつ延面積500㎡以下(旧4号建築物の木造規模)
2階以下かつ延面積500㎡以下(旧4号建築物の木造規模)
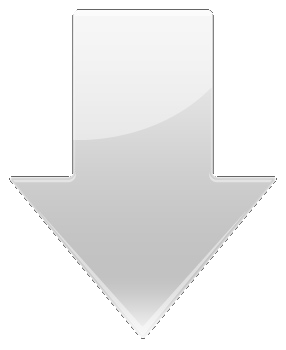
-
非木造
- 改正後
-
平屋かつ延面積200㎡以下(木造・非木造に関係なく、新3号建築物の規模として統一)
以上から、改正前までは一部審査を省略できたが改正により省略できなくなった建築物は、木造2階建て以下かつ延面積500㎡以下であり、但し平屋かつ延面積200㎡以下を除いたものである。(都市計画区域の区域内)。
なお、本制度は建築確認が必要な新3号建築物(改正前であれば旧4号建築物)に対して受けられる制度なので、新築だけでなく、増築、改築及び移転でも対象となる。
その一方で、大規模修繕や大規模模様替えについて、改めて整理しておくと次のとおりである。
大規模修繕や大規模模様替えに於いては、建築と異なり、都市計画区域等の区域外どころか区域内でも建築確認が不要になる建築物があり、それが、改正前の4号建築物であり改正後の3号建築物である(つまり、新3号建築物は、本制度とは無関係)。
視点を変えて、都市計画区域等の区域内に対する旧4号から新2号に変わった建築物を考えると、建築に於いては改正前から建築確認が必要であったので審査省略制度の対象から外れるだけであるが、大規模修繕や大規模模様替えに於いては改正前では不要であった建築確認が必要になり、しかも審査省略制度の対象外となる。つまり、区域内に於ける旧4号から新2号に変わった建築物については、大規模修繕や大規模模様替えは建築に比べ改正の影響が大きくなっている。
![]() 一部審査省略となる建築物規模の見直し(都市計画区域等の区域内)
一部審査省略となる建築物規模の見直し(都市計画区域等の区域内)
![]()
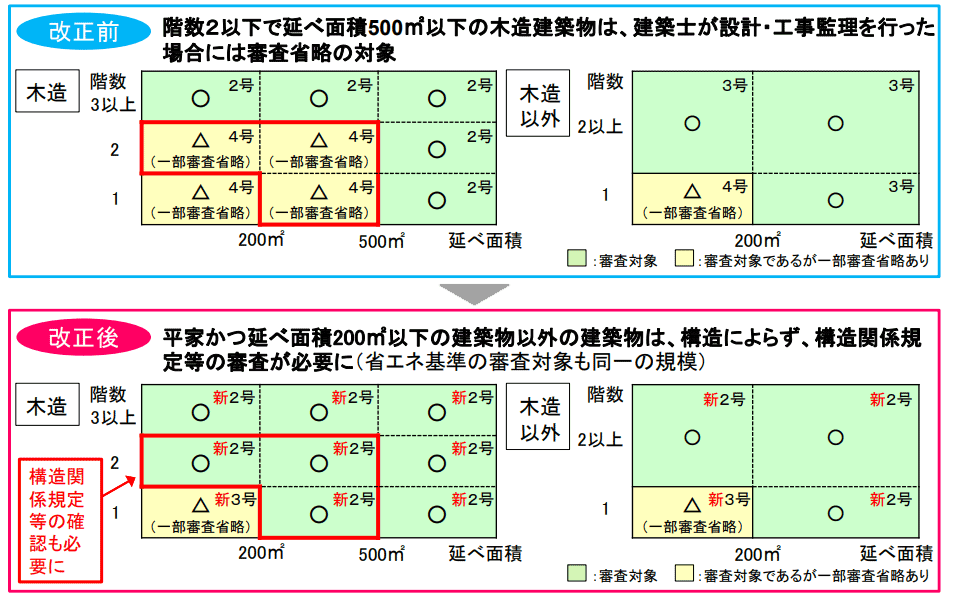
![]() 建築確認・検査に於ける審査項目の見直し
建築確認・検査に於ける審査項目の見直し
![]()
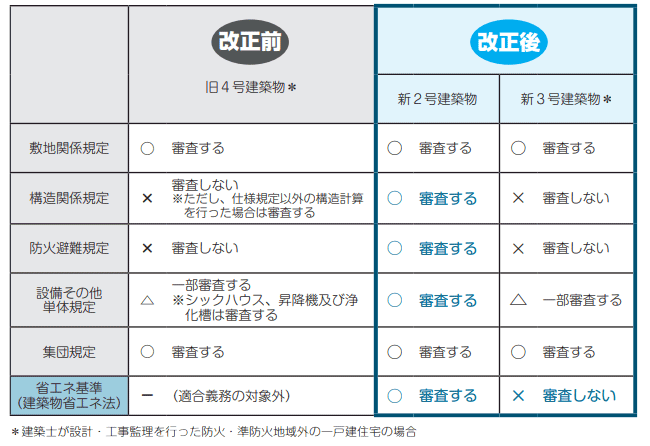
省エネ基準
建築物の建築をしようとする時は、省エネ基準に適合させなければならなく、この規定は建築基準法6条1項の関係規定とみなされる[建築物省エネ法10条]。従って、建築確認に於いて、基準に適合している旨の適合判定通知書がなければ、確認済証を交付することができなくなっている。
建築物省エネ法の改正により、新築・増改築(修繕・模様替えは対象外)をする場合は、原則として全ての建築物に対し、省エネ基準への適合が義務化されることになった(2025年4月1日施行)。これにより、原則着工前に「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」を受け、確認申請の際に適合判定通知書を提出する必要がある。
但し、省エネ基準には、計算によらず容易に基準への適合性を確認できる「仕様基準(住宅用途のみ)」が定められており、省エネ基準適合を「仕様基準」で確認する場合には、建築確認の中で省エネ基準への適合性を審査するため、省エネ適判が不要となる。従って、手続きの流れは次の2つに分かれる。
- 省エネ適判が必要な手続きの流れ
- 計算により「省エネ性能確保計画」を作成する場合、省エネ適判を受ける必要があり、手続きの流れは次のとおりである。
-
 省エネ適判が必要な場合のフロー(計算による場合)
省エネ適判が必要な場合のフロー(計算による場合)

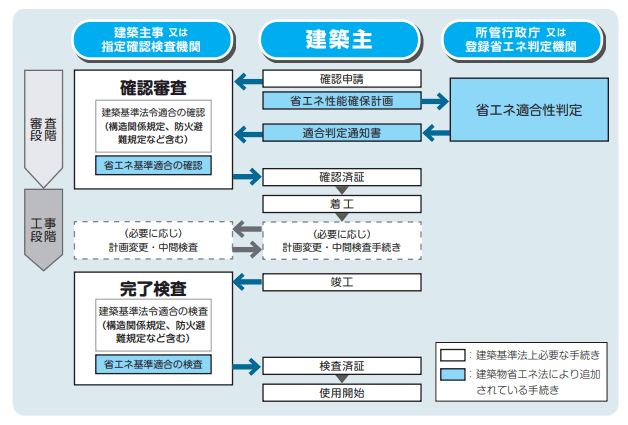
- 省エネ適判が不要な手続きの流れ
-
省エネ基準適合を「仕様基準」で確認する場合には、建築確認の中で省エネ基準への適合性を審査するため、省エネ適判が不要とる。この時の手続きの流れは次のとおりである。
 省エネ適判を要しない場合のフロー(仕様基準による場合)
省エネ適判を要しない場合のフロー(仕様基準による場合)

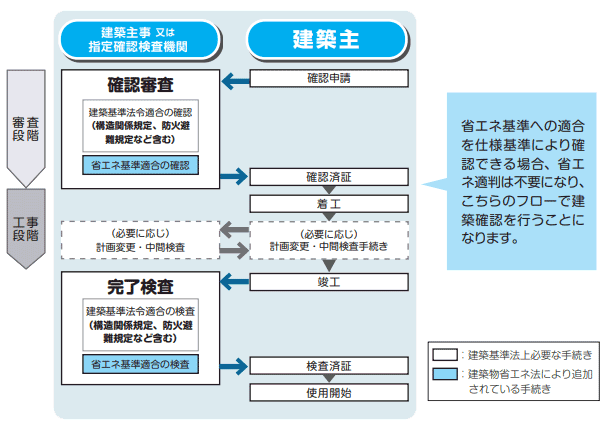
なお、10㎡以下の新築・増改築は基準適合の対象外である。また増改築に於ける基準適合の対象範囲は、改正前は建築物全体であったが、改正後は増改築部分のみで良いことになった。また、都市計画区域等の区域内の新3号建築物(平屋建てかつ延床面積200㎡以下の建築物)は、基準適合の対象ではあるが、省エネ適判が不要となる。
構造関係等
木造建築物に於ける省エネ化等による重量化に対応するため、建築基準法施行令等の改正を行い、次の構造関係等の見直しが行われた。
- 壁量基準の見直し[令46条4項](2025年4月1日施行)
- 柱の小径基準の見直し[令43条1項](2025年4月1日施行)
- 構造計算対象の見直し(2025年4月1日施行)
- 小規模な伝統的木造建築物等の構造計算適合性判定の合理化(2025年4月1日施行)
- 住宅の採光規定の見直し(2023年4月1日施行)
改正による影響
旧4号から新2号に変わる建築物の新築に対して改正前後で比較すれば、改正前であれば不要だった建築確認や審査が、改正後では必要になることにより、費用が増加したり、建築確認の手続きが長引き、工事着工が遅れたりすることが考えられる。このようなことは、想定内のことであり、また改正された以上は受け止めるしかない。
注意しなければならないことは、旧4号から新2号に変わった既存建築物の売買である。と言うのも、次のようなケースが考えられるからである。
このような物件は、購入前の新築時に於いて建築確認を取っていなかったり、一部審査を省略(図書の提出を省略)しているが、購入後に買主が増改築等を行う際は、新築時に省かれた建築確認や審査を受けなければならなくなる。また、今回の改正により、例えば構造上の問題で既存不適格建築物※3になっているケースも有りえ、更に言えば、新築時は図書の提出を省略できても保存義務があるが、保存していないケースも有りえ、あるいは審査省略を良いことに拡大解釈し、建築基準法令に抵触する建築物を新築し違反建築物※4になっているケースも有りえる。
そうなると、買主が増改築等を行おうとした時に、図書が用意できなかったり是正工事ができなかったりなど、建築確認のハードルが想定外に高いことを思い知らされ、増改築等を断念せざるを得なくなる可能性もある。
従って仲介業者の立場で捉えると、改正により旧4号から新2号に変わった建築物を売買する場合は、買主が購入後に増改築等を行う前提で購入することが分かっていれば、売買契約に当たり上記のようなリスクを調査し、買主からリスクの容認を取っておくべきである。そうしないと、買主から、売主は契約不適合責任を追及され、また仲介業者は契約不適合責任を追及されることはないものの、調査義務違反や説明義務違反と言う形で責任を問われる可能性がある。
