瑕疵の種類
瑕疵とは目的物が通常備ていなければならない品質・性能を欠いていることであるが、平たく言えば「傷」や「欠陥」のことである。不動産取引に於ける瑕疵は、物理的なことだけ指すのでなく、次のものが挙げられる。
- 物理的瑕疵(e.g. 雨漏り、土壌汚染)
- 法令的瑕疵(e.g. 建築制限)
- 心理的瑕疵(e.g. 事故物件)
- 環境的瑕疵(e.g. 近隣の騒音、異臭、及び暴力団事務所)
瑕疵担保責任とは
売買の目的物に隠れた瑕疵が契約前から存在していた場合は、売主は買主に対し責任を負う必要があり、この責任のことを「瑕疵担保責任」※1と言う。
この時、買主は売主に対し次のことができる(民法570条により566条準用)。
- その瑕疵のために、売買契約の目的が達成できない時は、契約解除することができ、併せて損害賠償請求をすることができる。
- 一応、目的が達成できたが損害を受けた時は、損害賠償請求をすることができる。
瑕疵担保責任発生の要件
瑕疵担保責任が発生する要件は、買主の善意(民法566条)・無過失(判例)である。つまり、買主は瑕疵の存在を知らなく(善意)、かつ知らなかったことについて過失がない(無過失)必要がある。この状況の瑕疵のことを「隠れた瑕疵」と言う。
例えば次の場合は、どちらも隠れた瑕疵に該当しないことから売主の瑕疵担保責任は発生しない。
- 契約締結前に、買主が瑕疵の告知を受けていた場合。買主は瑕疵の存在を知っていた(悪意)ことになる。
- 買主が取引界で要求される普通の注意を払って不動産を見ていれば発見できる瑕疵の場合。例え瑕疵の存在を知らずに契約締結したとしれも過失があったことになる。
なお、民法の原則は損害の発生に対し過失責任主義であるが、民法の特例として「無過失責任」となる場合があり、瑕疵担保責任がその1つである。従って、売主が隠れた瑕疵の存在を知らず売却したとしても、買主に対し瑕疵担保責任を負う。
2020年4月1日から施行される改正民法では、「瑕疵」や「隠れた瑕疵」と言う表現がなくなり、「契約不適合」と言う表現に取り込まれる。これに伴い「隠れた瑕疵」が要件であった「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更され、売主が契約内容に適合した不動産を引渡さない場合は、「債務不履行責任」を負うことになる。なお、この時の「債務不履行責任」は通常どおり、売主の過失が要件となり、無過失の立証責任は売主が負わなければならない。
瑕疵担保責任を行使できる期間
買主が瑕疵担保責任を行使できる期間は、瑕疵の事実を知ってから1年以内である(民法570条により566条準用)。ただ、この条件を満たせば永久に請求権が存続するとなると売主に過大な負担を負わすことになることから、瑕疵担保の損害賠償請求権は債権の消滅時効(民法167条)が適用され、引渡しを受けてから10年以内に行使する必要がある(判例)。
なお、瑕疵担保責任に関する民法の規定(570条、566条)は任意規定なので、これらの規定と異なる特約を付けることは可能である。例えば、瑕疵担保責任を軽減する「行使できる期間は引渡しから6ヶ月以内」としたり、瑕疵担保責任免責の「瑕疵担保責任を一切負わない」としたりすることが可能となる。
但し、瑕疵担保責任免責の特約を付けたとしても、売主が瑕疵の存在を知りながら買主に告知していなかった場合は、売主が知っていた瑕疵の部分に限り特約は無効となり、売主は瑕疵担保責任を負わなければならない(民法572条)。
また、売主が宅建業者の場合は、瑕疵担保責任を行使できる期間を引渡しから2年以上にする特約を除き、民法より買主が不利になる特約は無効となる。無効になった場合は原則に戻り、事実を知ってから1年以内であれば行使できることになる(宅建業法40条)。但し、買主も宅建業者の場合は、これが適用されないので買主が不利になる特約も可能となる(宅建業法78条)。
参考までに、特に古い建物の場合は経年劣化や自然損耗と見るべきか、あるいは隠れた瑕疵とみるべきかでトラブルになり易いため、売主の立場で考えると可能であれば瑕疵瑕疵担保責任免責の特約を付けた方が無難である。
他の法律の瑕疵担保責任
上記で述べたことは民法・宅建業法の規定を元に解説したものであるが、それら以外の法律でも瑕疵担保責任を規定しているので、以下に他の法律の規定内容を解説する。
消費者契約法
消費者契約法により、不動産売買契約の瑕疵担保責任の特約が無効になる場合があり(8条、10条)、その概要は次のとおりである。
消費者契約法とは、消費者と事業者※2との間で締結される契約について、消費者の保護を図るための特例を定めた法律である。
この法律では、代替措置を設けた上で瑕疵担保責任を免責する場合を除き、瑕疵担保責任免責の特約は無効となる。更に、瑕疵担保責任を軽減する特約も無効になることがある。例えば、宅建業者でない事業者が売主となった土地の売買契約に於いて、瑕疵担保責任の追及可能期間を引渡しから3ヶ月以内とした特約が、消費者契約法10条違反として無効になった判決もある。
なお、不動産売買契約に於いて、当事者の関係と適用される法律(民法・宅建業法・消費者契約法)を整理すると下表のとおりとなる。
| 売主 | 買主 | 適用法律 |
|---|---|---|
| 消費者 | 消費者 |
民
|
| 消費者 | 宅建業者でない事業者 |
民
消
|
| 消費者 | 宅建業者 |
民
消
宅
|
| 宅建業者でない事業者 | 消費者 |
民
消
|
| 宅建業者でない事業者 | 宅建業者でない事業者 |
民
|
| 宅建業者でない事業者 | 宅建業者 |
民
宅
|
| 宅建業者 | 消費者 |
民
消
宅
|
| 宅建業者 | 宅建業者でない事業者 |
民
宅
|
| 宅建業者 | 宅建業者 |
民
宅
|
住宅品質確保法
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、「住宅品質確保法」と言う。なお、略称として「品確法」とも言われている。)には、瑕疵担保責任の期間が規定されていて(94条~97条)内容は次のとおり。
まず、本法律の適用を受けるのは、全ての住宅でなく、新築住宅のみである。
新築住宅の取引に於いて、売主及び請負人は建物の基本構造部分の隠れた瑕疵に対し10年間の瑕疵担保責任を負わなければならない。また、特約で期間を20年間まで延長することができるが、10年間より短くすることはできない。10年間より短い特約を付けて契約締結した場合は、その特約は基本構造部分に限って無効となり10年間となる(基本構造部分以外に関しては特約が有効)。
なお、10年間といっても、隠れた瑕疵を発見し例えば5年も経過してから瑕疵担保責任を請求されたものまで責任を負わなければならないとなると公平でないので、本法律はそこまでの行使を認めていない。従って、発見してから1年間行使しなければ、引渡しから10年間以下であろうと行使できないと解釈されている(トラブル予防の観点から、「発見してから1年以内に行使しなければならない。」旨の特約を付けるようにした方が良い)。
この法律の対象となる契約は次のとおり。
- 注文住宅
- 工務店(請負人)と施主(注文者)との間の請負契約(施主が工務店に対し行使可能)
- 建売住宅
-
- 工務店(請負人)と宅建業者(注文者)との間の請負契約(住宅を発注した宅建業者が工務店に対し行使可能)、及び
- 宅建業者(売主)と住宅取得者(買主)との間の売買契約(住宅取得者が住宅を販売した宅建業者に対し行使可能)
また、基本構造部分である「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」について、木造の戸建住宅(在来軸組工法)を例にして表すと下図のとおり。
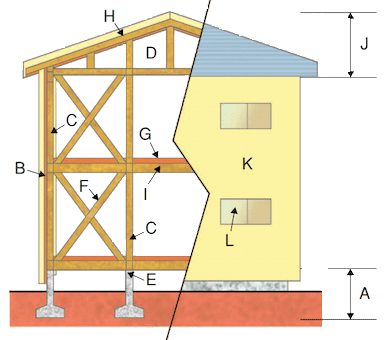
| 構造耐力上主要な部分 | |
|---|---|
| A | 基礎 |
| B | 壁 |
| C | 柱 |
| D | 小屋組 |
| E | 土台 |
| F | 斜材 |
| G | 床板 |
| H | 屋根版 |
| I | 横架材 |
| 雨水侵入を防止する部分 | |
|---|---|
| J | 屋根 |
| K | 外壁 |
| L | 開口部 |
これまでの解説で分かるように、法律により異なる瑕疵担保責任の追及可能期間が定めらている。整理すると、下表のとおり。
| 法律 | 追及可能期間 | 適用要件 |
|---|---|---|
| 民法 | 隠れた瑕疵を知ってから1年間で、かつ引渡しから10年間。なお、特約で免責や軽減も可能。 | |
| 宅建業法 | 特約で引渡しから2年間(以上)に変更可能。 |
売主:宅建業者 買主:宅建業者以外 |
| 住宅品質確保法 | 引渡しから10年間で、かつ隠れた瑕疵を知ってから1年間。なお、特約で引渡しから20年間まで延長可能。 | 目的物:新築住宅 |
住宅瑕疵担保履行法
上記で示したとおり、新築住宅の買主は少なくも引渡しから10年間の瑕疵担保責任を行使できるようになっている。しかし、長い10年の間に売主側の会社が倒産したり、業績が傾き損害賠償請求に対応できる資力がなくなっている可能性もある。このような事態を対処するために「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(略して「住宅瑕疵担保履行法」)がある。
この法律により、売主側が万が一、資力がなくなっても瑕疵担保責任を履行できるように、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられている。
瑕疵担保責任と混同し易い用語
瑕疵担保責任絡みで混同し易い次の用語もあり、それらの用語を曖昧に理解していると瑕疵担保責任の法律効果があると勘違いしかねないので整理しておく。
危険負担
危険負担とは、双務契約※3を締結してから履行する時期が来るまでに、債務者の責任でない理由で、その債務が履行不能になるリスクに対する負担のことである。その場合にどちらが負担しなければならないか重要な問題である。
例えば小売店で商品を購入(売買)をするのであれば、買主が陳列棚から購入商品を選んだ時点で商品が特定される(特定物になる)が、速やかに履行される(レジで代金を支払い商品を受け取る)ので当事者は危険負担の扱いを問題するまでもない。しかし、特定物が不動産となると、売買契約締結から履行まで数カ月掛かることも多く、その期間に自然災害が発生すれば売買の目的物である建物が毀損(壊れる)、滅失(建物自体が無くなる)リスクがあり、無視する訳にはいかない。
民法上に於ける特定物の売買契約では、特定物の引渡しを受ける権利のある債権者が、滅失・毀損の危険負担を負う必要がある(民法第534条:危険負担の債権者主義)。つまり、売主は自然災害で建物が一部壊れても補修することなく引渡せば良く、建物自体が無くなっても建物を建て直して引渡す必要もないにも関わらす、買主は売買代金を支払う必要がある。
ただ、これだと買主はまだ使用できなかった物に対してリスクを負う必要があり余りにもバランスが悪く、また民法第534条は任意規定なので、売買契約書に売主が危険負担を負う特約を付けるのが常識である(実際の契約書では、特約欄に記載されているのでなく、本文の条文として記載されていることが多い)。買主の立場に立てば、この特約が契約書に記載されていることを確認して契約締結すべきである。
この危険負担と瑕疵担保責任は混同し易いが、両者は問題の原因が発生した時期に違いがある。危険負担は契約締結から引渡しを受けるまでの間で問題(リスク)が発生し、瑕疵担保責任は契約前に既に問題(瑕疵)が発生している。
2020年4月1日から施行される改正民法では、民法第534条(危険負担の債権者主義)が削除され、債務者主義に統一される。当事者の責任でない理由で債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができることになり(改正民法536条)、例えば、建物が自然災害で滅失(全壊)し、売主が建物を引渡しできなくなった場合は、買主は(特約が付いていなくても)代金支払いを拒み契約解除することもできるようになる。
現状有姿
不動産の売買契約書に於いて「現状有姿」と言う用語が使われることがある。例えば「現状有姿売買である。」、「現状有姿にて引渡す。」である。ただ、「現状有姿」は法律用語でなく、不動産業界でも明確な定義がある訳でないため、売主・買主・仲介業者間で異なる解釈をしてしまう可能性もあり注意が必要である。
現状有姿売買で誤解され易いのは、買主は今の状態のまま引き渡されることに了解したのだから、引渡し後に隠れた瑕疵が見つかっても、売主に責任追及できなくなると判断することである。
現状有姿の妥当な解釈は、次のとおりである。
買主は、現状有姿と言われれば、「今の状態のまま引き渡す」ことだと理解できるが、「隠れた瑕疵」を免責(瑕疵担保責任免責)する重大な効果まで発生していると判断して契約締結していと言い難い。従って、現状有姿は「今の状態のまま引き渡す」と言っているだけで、それ以上の意味を含んでいなく、瑕疵担保責任免責効果がないとみるべきである。
以上から、瑕疵担保責任を軽減あるいは免責するのであれば、曖昧な表現の「現状有姿」を使うのでなく、「瑕疵担保責任」をどう扱うか明確に表現すべきである。
なお、本解説に於いて「今の状態」と表現したが、これにも次のような異なる解釈ができる。
- 契約締結から引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡すと言う意味の現状有姿。
-
これはどのような状況を想定しているのか私自身把握している訳ではないが、現実的な思い付く具体例として付帯設備※4の次の2つの状況がある。
-
不動産取引の場合に契約締結から引渡しまでに数カ月掛かることも多く、売主は引渡し時までに整理すれば良いとの思いから、契約締結時に存在していた付帯設備を運び出し、引渡し時になくなっていることがある。このような状況を考慮し、契約締結時でなく引渡し時に存在する付帯設備のみ引渡すと言う意味の現状有姿。
ただ、運び出した付帯設備が民法の従物に当たれば買主の物になるので勝手に運び出せなく、また従物でなくても契約締結時に存在していた付帯設備が無くなっていればトラブルになり易い。
-
通常の買主は付帯設備の有無や性能を確認してから契約締結することになるが、買主が引渡し時に契約時の性能が維持できていないと判断した場合に契約違反と主張する可能性がある。著しい性能劣化でない限り判断が難しくトラブルになり易いため、このような状況を考慮し、契締結時でなく引渡し時の性能で引渡すと言う意味の現状有姿。
なお、付帯設備は売買の目的物の付録的なものと捕えることができ、また新築建物でない限り付帯設備は中古品なので、売主に瑕疵担保責任を負わせることは適切でないとの考えがあることから、付帯設備に対し瑕疵担保責任免責の特約を付けることは無理もないことと考える。
上記のどちらの意味合いであろうと、トラブル防止のため、引渡す付帯設備とその設備の使用可否・不具合等を明記した付帯設備一覧表を契約書に添付し、また付帯設備の瑕疵担保責任についても明確にすべきである。
-
- 売買契約締結時に買主に明らかになっている瑕疵を補修せず引渡すと言う意味の現状有姿。
-
この瑕疵については買主は悪意があるので隠れた瑕疵に該当しなくなり、買主は瑕疵担保責任を行使できない。
- 新たに土地の造成工事や建物のリフォーム等をせず、契約締結時の状態で引渡すと言う意味の現状有姿。
-
これは瑕疵について何も触れていないので、買主は隠れた瑕疵があれば瑕疵担保責任を行使できる。
いずれにせよ、契約書に「現状有姿」が記載されていれば、契約書を作成した本人にどのような意味で使っているか確認し、状況によっては明確な表現に訂正するように要求すべきである。
参考までに、売買契約書に「現状有姿につき、売主は瑕疵担保責任を負わない。」と記載されることもあるが、現状有姿に瑕疵担保責任免責効果がないことを踏まえれば表現が可笑しいと見るべきである。
仲介業者の責任
宅建業者が不動産売買の仲介を行った場合、瑕疵で責任問題になりうるのは、瑕疵担保責任でなく、債務不履行責任や不法行為責任である。これらは、瑕疵担保責任と異なり、仲介業者の過失が要求され、瑕疵に対し仲介業者としての善管注意義務違反があったか否かが焦点になる。
また、この時の仲介業者が負っている注意義務の程度は、瑕疵の種類により次のように異なる。
- 物理的瑕疵
-
建築や地盤の専門家でないことから、普通の一般人の注意義務で良いとの考えが基本スタンスである。従って、目視や売主の情報からは瑕疵の存在を認識できない場合は、法的責任まで問われない傾向がある。
- 法令的瑕疵
-
専門家としての高度な注意義務が問われる。従って、役所への調査等を十分に行なった上で行動していないと、法的責任が問われる可能性が高くなる。
- 心理的瑕疵及び環境的瑕疵
-
基本的には物理的瑕疵に近いと思われるが、仲介するに当たって当事者の要望を十分に把握し、それに影響を与えそうな要因については、できる限り調査すべきである。
なお、仲介業者は不動産取引の専門家であることを踏まえれば、専門家としての通常の調査・注意義務が必要である。よって、所有者であった売主しか分からない様な隠れた瑕疵もあるので売主から(瑕疵の)告知書の提出を求めたり、目視の確認で良いと言っても不動産取引の専門家として注意深く見ることが要求される。
参考までに、瑕疵担保、債務不履行及び不法行為に於ける責任追及のし易さを比較すると次のとおり。
瑕疵担保は先に述べたとおり無過失責任なので、売主(被告)に過失がなくても追及できるが、債務不履行は売主(被告)が自身の過失なしを立証しなければならなく、不法行為は買主(原告)が売主(被告)の過失ありを立証しなければならない。従って、責任追及のし易さは、瑕疵担保、債務不履行、不法行為の順となる。
